週末にビンテージバイクで風を切って走るのは、まるで過去と現在を行き来するような面白い感覚です。現代のバイクにはない独特の魅力と風情があります。クラシックなデザイン、エンジン音、走行感覚はもちろん、手入れの手間さえも愛おしく感じられます。
ビンテージバイク歴20年以上の筆者としては、週末会社員の特別な趣味としてバイクに興味のあるあなたにとてもおすすめです。それは、機械と一体になる特別な体験です。
しかし、その魅力と引き換えに、特有の注意点や準備が必要です。壊れるかもしれないという覚悟を持ちつつ、しっかりとした準備をすれば、ビンテージバイクとの素晴らしい時間を楽しむことができます。
本記事では、筆者の実体験を交えながら、ビンテージバイクを楽しむために気を付けるべきポイントをご紹介します。壊れやすい部位への対策、電気系統の知識、そしてオイル漏れ対策などをお届けします。
壊れるかもしれないという覚悟:でもそれが旧車との付き合い方
いきなりビビらせてしまいそうですが、壊さずに乗り続けるには10年くらいはかかります。
バイク屋さんのように極度にバイクに偏った生活をしていない一般のライダーである筆者の経験ベースでば、10年乗り続けてやっと悪いところが洗い出されていく印象です。
ツーリングに出かけたときには、どこでどのような症状がでてもいいように心の準備は大切です。心の準備が完了したら、具体的にご自身が可能なレベルの対策を施していきましょう。
ロードサービスへの加入は必須条件
まずは、充実したロードサービスに加入しておきます。これは旧車・ビンテージバイクに乗るなら必須条件です。
JAFはバイクにも対応していますが、レッカーの無料搬送距離が短いのが難点です。
特にマニアックな旧車の場合は、面倒みてくれるショップが少ないため自宅や行きつけのショップに搬送してもらうことになるので、レッカーサービスの距離が長いサービスを選ぶことをおすすめします。
ロードサービスは、バイクの任意保険に付帯されているケースも多いため、保険を選ぶ際に重要視することをおすすめします。
最低限の工具を持っておこう!
次に、最低限の工具を車載することです。
経験が浅く、バイクを自分で触る機会がこれまでなかったので工具を持っていてもなにもできないよというひともいるかもしれません。
たしかに、そういう面もあるかもしれませんが、ドライバー、ペンチ、ニッパー、小型のモンキーレンチ、バインド線(ビニル被覆付の針金)、ビニールテープ、作業用の手袋程度はいつも車載して走る方がよいと思います。
- ドライバー(+)
- ペンチ
- ニッパー
- モンキーレンチ
- バインド線(ビニル被覆付の針金)
- ビニルテープ
ツーリング先の休憩中に、ネジが緩んでいるのを見つけて増し締めしたとか、部品がはずれかかっているからテープで仮補強した なんてことは残念ながらよくあることです。
レザーマンを持つという選択
ここで、工具へのこだわりがでてくると、さらにあなたの趣味の世界は広がりを見せます。SNAP-ONやKTCなどのブランドものの工具をつかったり、高価ではなくとも長く大切にしたりと、工具の世界までもが趣味となり、あなたの人生をより一層充実したものにしていきます。

上記で紹介したツールを幅広くカバーできるアイテムが「レザーマン」です。
レザーマンを1つ持っておくとコンパクトに多くの工具機能をかっこよく持ち運ぶことができてとてもおすすめです。筆者はバイクに乗る際に、かならずレザーマンをポーチに忍ばせます。
詳しくは過去に紹介している記事をご覧ください。
プラグレンチは不要か?
バイクのいろんな書籍などで、プラグレンチを持参するように記載がありますが、もちろん持っているに越したことはありません。しかし、プラグレンチでプラグをはずしてすぐに何かできることは比較的少ないように思います。筆者は、プラグレンチをもってツーリングに出かけますが、プラグレンチで雑にプラグを取り外してしまいネジ山をくずしてしまい、不動車への道をみずから突き進んだ経験があります。
いずれにしても、旅先で壊れること前提の準備が必要なうえに、壊れた後の修理に一定の期間が必要になることが多いことも旧車・ビンテージバイクとの付き合い方の一つとして理解しておくとよいでしょう。
そのため、壊れやすい部位などの傾向をつかんで、心地よくツーリングできるようになるのに10年くらいはかかるというのが経験上の結論です。
筆者はそこにたどり着くまでに、その壊れ方にも愛おしさを感じるへんなやつだったので、まぁまぁ楽しかった思い出が多いのですが、ようやく10年以上乗り続けてあまり旅先で壊れなくなっていますので今はツーリングにあまり不安を持たなくなりました。
電気にかかわる知識:エンジンやミッションより電気系統が弱点
エンジンやミッションなどが壊れることより、電気回路関係のトラブルが圧倒的に多いです。
電気関係のトラブルの主なものは、配線の断線や、端子の接触不良、電球切れや整流器・レギュレター(バッテリーの充電に必要な部品)の不具合、バッテリーの寿命などです。
どれも、エンジン自体が壊れたりするのに比べると対処は簡単なんですが、経験上、発生頻度はかなりのものです。
わたしは1975年ころのYamahaのオートバイに乗っています。これまで何度も電気系統に悩まされてきました。過去記事にも多く電気系統への対応事例を登場させています。

電球切れ程度であればすぐに対応できますが、どこの配線が切れたのかなど探すことに費やした時間のなんと多いことか。いまは、弱点だった部品をすこしずつ新しいものに交換し続け、ようやく不安がある程度払拭されてきました。
まだまだ50年くらい前の電気配線が残っているので、どこでどうなるかひやひやしていますが、それでもこのバイクとは20年以上の付き合いとなりました。壊れやすい部位にはそれなりに対策を講ずることができてきたと自負しています。

私の場合、最初のころ小学校の理科で習った電球が点く程度の回路しかピンときていませんでしたが、経験しながらバイクに使われる電気回路に関する知識がある程度わかるようになってきました。
もちろん最初から少しくらいはバイクの電気回路に関わる知識や感性をもっておくと、楽に旧車・ビンテージバイクと付き合っていけるといえます。
オイル漏れ程度はある:ガレージにマットなどを敷く
旧車・ビンテージバイクは、、、はっきりいってオイルは漏れます!
このことを認識したうえで付き合っていきましょう。
いろんな部分にガスケットやオイルシールが使われていて、どこからともなく漏れてきます。
ガレージはオイルのシミだらけです。
そのことはきちんと事前に頭の整理を行ったうえで旧車・ビンテージバイクとお付き合いください。
オイルがもれている部位がある程度特定できる場合は、その部分のガスケットやシールを新品に交換するなどして対応が可能です。
しかし、古い金属のケースを完全密封状態にするにはかなりの時間を要することが想定できます。
そこで、おすすめなのはガレージにはオイルパン(オイルの受け皿)をエンジン下、ミッション下にひくことです。
オイル漏れの箇所が特定できない場合には、バイクの下全体的にマットを引くことをおすすめします。
あまりお金をかえずにできる方法としては、新聞紙や段ボールを広めに引いておくことがあります。他にもクッキーが入っていた缶をオイルパンとして使ったり、100均のトレーをオイルパンに使ったりすることで代用できます。それぞれ見た目の問題を解決する必要は生じますが、安くあがるのでお勧めです。
オイル漏れは絶対にあることを念頭において旧車・ビンテージバイクと付き合っていきましょう。




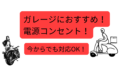
コメント